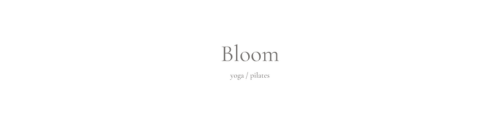アシュタンガヨガ八支則の完全ガイド|2025年版・初心者でも実践可能な8つのステップ
忙しい現代生活で心が疲れていませんか?
アシュタンガヨガの八支則は、2000年以上前から伝わる心と体を整える8つの実践法です。
この記事では、ヨガ初心者でも今日から取り入れられる八支則の具体的な活用法を、現役ヨガインストラクターが分かりやすく解説します。
この記事で分かること
- アシュタンガヨガ八支則の基本知識
- 現代生活での実践方法
- 心の性質「トリグナ」との関係
- 初心者向けの始め方
読み終わる頃には、あなたも八支則を使って心穏やかな毎日を送れるようになるでしょう。
アシュタンガヨガとは?初心者が知るべき基礎知識
アシュタンガヨガとは?初心者が知るべき基礎知識
「アシュタンガヨガって難しそう…」そんな風に感じていませんか?
実は、アシュタンガヨガは激しいポーズを取る流派ではなく、心と体を整えるための8つの段階的な実践法のことを指します。
サンスクリット語で「アシュト=8」「アンガ=支則(段階)」という意味で、私たちがよりよく生きるための"8つのステップ"なのです。
アシュタンガヨガの特徴
- 2000年以上の歴史を持つヨガ哲学
- 心の平穏と身体の健康を同時に目指す
- 初心者でも段階的に実践可能
- 現代のストレス社会に特に有効
この記事では、現役ヨガインストラクターの私が、初心者でも理解しやすいよう丁寧に解説していきます。
アシュタンガヨガ八支則|心と体を整える8つのステップ詳細解説
以下が、アシュタンガヨガの8つの実践段階です。
① ヤマ(禁戒):日常生活で避けるべき倫理的な実践
正直であること、暴力をしないこと、盗まないことなど、社会との関わりで大切にすべきこと。
今日からできる実践
- 他人を批判しそうになったら一呼吸置く
- 約束の時間を守る
- 無理なスケジュールを組まない
- 嘘をつかずに正直に話す
② ニヤマ(勧戒):日常生活で積極的に行うべき行動や習慣
清潔に保つ、満足する、学ぶ、自分を律するなど、内面を整える習慣のこと。
今日からできる実践
- 整理整頓をして身の回りを整える
- 今ある環境や状況に感謝をして過ごす
- 目の前のことに誠実に取り組む
- 自己啓発本を読む
③ アーサナ(坐法):ヨガのポーズ
体を整え、心を集中しやすくするための動き。健康や柔軟性だけでなく、内面への集中にもつながります。
今日からできる実践
- 立った状態から前屈(立位の前屈)
- 四つん這いの状態から、お尻を高く持ち上げ、V字を作る(下向きの犬のポーズ)
- 寝転がった状態で、両膝を立て、左右に倒す(ワニのポーズ)
④ プラーナヤーマ(調気法):呼吸のコントロール
呼吸を整えることで、心も穏やかに。自律神経のバランスを整える効果もあります。
今日からできる実践
- 座ったまま目を閉じて呼吸に意識を向ける
- 仰向けで目を閉じ、腹式呼吸をする
- あぐらで座り、目を閉じてゆっくりと鼻呼吸を繰り返す
⑤ プラティヤハーラ(制感):感覚を内側へ向ける
外の刺激から離れて、自分の内面を感じる練習。
今日からできる実践
- 寝る2時間前にはスマホから離れる(デジタルデトックス)
- 食事をゆっくりと丁寧に味わう
- アロマを焚いてリラックスする
⑥ ダーラナ(集中):一点に心を定める
瞑想の手前の段階。1つのことに集中する力を養います。
今日からできる実践
- 呼吸に意識を向ける
- ろうそくの火を見つめる
- 音に意識を向ける
⑦ ディアーナ(瞑想):心を深く静める
思考の波が静まり、ありのままの「今」を感じられるように。
今日からできる実践
- ダーラナで集中できたことを継続する
⑧ サマーディ(三昧):悟り・至福の境地
心と体が完全に調和した、深い平穏の状態。
到達には時間がかかりますが、日々の小さな実践が大切です。
八支則を現代生活に活かす3つの実践法【すぐ始められる】
八支則は2,000年以上前の教えですが、
実は、現代の忙しい毎日にこそ取り入れたい“生き方のヒント”でもあります。
たとえば――
- 情報に疲れた時には「制感(プラティヤハーラ)」を意識してデジタルデトックス。
- 怒りが湧いた時には「ヤマ」のアヒムサ(非暴力)を思い出す。
- 日常の中で「ニヤマ」の感謝や学びの姿勢を持つ。
そうやって、自分自身を見つめ直し、丁寧に生きる視点を八支則は教えてくれます。
心の性質トリグナとは?八支則との関係性を解説
心身を整えるには、日々の生活習慣も欠かせません。
ヨガ哲学では、心には以下の3つの性質(グナ)があるとされています。
サットヴァ(純粋性・調和)

純粋で穏やか。自制心が強い。
イキイキしていて向上心がある。
安定していてどこにも偏っていないバランスの取れた状態。
ラジャス(激性・動性)

エネルギッシュ。やる気に満ちて情熱的。
疲れていてもまだ大丈夫!と常にアクティブに動いてしまう。
バランスが崩れるとイライラしやすく、誰かと比べて妬みや嫉妬といった感情が出やすい。
タマス(怠性・無知)

やる気がなく常に眠気を感じている。
自分の利益のためなら他者を傷つけても何も思わない。
タマスの気質が高まると執着心が強くなり、過去の出来事にも根に持ってしまいやすい。
全てはバランス。偏りのない状態を目指そう!
この「トリグナ」は、私たちの考え方や選ぶ言葉・食べ物にも影響を与えていると言われています。
アシュタンガヨガの八支則は、これら心の性質を整え、サットヴァ=調和のとれた心に近づけていくための実践。
「なんだか疲れてるな」「気持ちがざわついているな」そんな時こそ、八支則を意識することで、
少しずつ、心が整い、自分の中心に戻れる感覚が得られるはずです。
日常で八支則を活かすためには、自律神経を整えることも大切。
よくある質問|アシュタンガヨガ八支則について
Q. アシュタンガヨガは初心者には難しいですか?
A. 全く難しくありません。八支則は段階的な実践法なので、まずは呼吸法やヤマ・ニヤマから始めることができます。
Q. どのくらいの期間で効果を感じられますか?
A. 個人差はありますが、多くの方が2-3週間の実践で心の変化を感じています。
アシュタンガヨガを始める方法|オンラインレッスンがおすすめな理由
八支則は「こうしなければならない」というルールではありません。
むしろ、自分を知るための“やさしい道しるべです。
今のあなたができそうなことを1つ、日常に取り入れてみてください。
呼吸に意識を向ける、部屋を整える、ヨガのポーズをひとつ丁寧に取る──
その小さな選択が、心と体を整え、毎日を豊かに変えていく一歩になります。
私のオンラインセッションでは、アシュタンガヨガの哲学に基づいた「美しく健康に生きるための習慣づくり」サポートしています。
「今の自分を変えたい」「心も体も整えたい」そう感じているあなたへ。
まずは【無料オンラインカウンセリング】で、今の不調や理想の姿を一緒に言語化してみませんか?
あなたも今日からアシュタンガヨガを始めませんか?
「八支則を実践してみたいけど、一人では続けられるか不安…」
そんなあなたのために、私のオンラインセッションでは
✅ アシュタンガヨガ哲学に基づいた個別サポート
✅ あなたのライフスタイルに合わせた実践プラン
✅ 心と体の変化を実感できるサポート体制
今なら無料オンラインカウンセリングで
- あなたの現在の心身の状態をチェック
- 最適な八支則実践プランを提案
- 3ヶ月後の理想の自分を一緒に設計